現代特有の「脳疲労」を防ぐ新しい休み方
企業が「デジタルデトックス」を推進することで、
社員の脳疲労を軽減し生産性が向上する。
心身の健康を守り、創造性を高める『新しい休息法』とは?
過去にデジタル疲れに悩まされた経験から、
現在では一般社団法人日本デジタルデトックス協会の理事である森下氏に
「デジタルデトックス」の重要性と意義について解説いただきました。
一億“総疲労”社会の到来
■日本人の8割は「疲労」を自覚
一般社団法人日本リカバリー協会が主導した調査「日本の疲労状況2024」では、10万人以上の回答者のうち実に8割が「疲れを自覚している」と回答しています。特に、20〜40代の疲労レベルが顕著に高まっているようです。
かねてから、日本では過労問題が取り沙汰され、「ストレス社会」と呼ばれて久しいものの、ビジネスパーソンの多くはいまだ耐え難い疲労を感じているのではないでしょうか。
大量の情報を処理するデジタル社会で蓄積する疲労は、これまでの肉体的な疲労とは異なる類のものです。
言うまでもなく、疲れている状態とは「絶対的に劣位の状態」です。疲れたままでは、仕事のパフォーマンスを上げることはおろか、日常生活を幸福に送ることすら難しくなります。
しかし反対に、エネルギーが充足した状態であれば、同じ時間でこなせる仕事の質も上がりますし、事業を推進する新たなアイデアも生まれやすくなるでしょう。
そう考えると、現代に生きる私たちは、まずキャパシティの確保から始めるべきではないでしょうか? 多くの人は、あるいは組織は、ケイパビリティ(スキル・能力)を高めるために、コストをかけています。それは重要なことながら、そもそもこれだけ多くの人が「疲れている」と自覚している昨今、まずはエネルギー充電の時間をとるのが先決だと私は考えています。
ですから、私は2024年に上梓した拙著『戦略的暇──人生を変える新しい休み方』のなかで、ウェルビーイング(福利厚生)プログラムを闇雲に導入するのではなく、組織が休息について考え、新しい休み方を推奨していくべきだと提言しています。
ではデジタル社会に必要な「休息」とは何なのか──皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
■ほぼデジタルライフに生きる現代人
2018年、スマホやPCの利用時間を計測するアプリ「レスキュー・タイム」が同アプリのユーザー1万1,000人を対象に行った平日のスマホ利用の調査によると、1日の平均利用時間は3時間15分でした。
加えて、アキュビュー(J&J社)が2,000人の事務職員を対象に実施した調査を見ると、対象者の仕事中のPCの利用時間はなんと年間1,700時間。1日(平日のみ)に換算すると、約6時間30分です。調査に参加した方の37%は、「モニターの見すぎで頭痛に悩んでいる」とすでに自覚症状がありました。
試算してみると、一般的なスマホユーザーかつ仕事でPCを利用する方であれば、デジタル機器に触れている時間は、試算にして9時間45分以上。起きているうちの半分以上は「モニターの前に居る」のです。年間で考えると、約2,340時間──つまり、約3ヵ月はデジタル機器を使っているとも考えられます。
職種を問わず、多くの人たちが仕事でも余暇でもデジタル機器を使って仕事を進め、コミュニケーションをとっています。しかし、常に新たな情報に反応し、取捨選択をする行為は脳に大きな負荷をかけています。ほぼデジタルライフに生きる私たちはこの脳に蓄積する疲労──脳疲労をケアする必要があるのです。

■現代人が注意すべき脳疲労
身体の他の部位と同様、脳も情報処理をこなすことで疲労が溜まります。デジタル機器は多くの情報に溢れており、脳はそれらに強く反応します。手足の筋肉の疲れは自覚しやすいものの、脳の疲れにはなかなか気がつけません。余暇の時間にSNSを見たり、仕事中のちょっとした息抜きにニュースをチェックしたりしていると、身体は動いていないので「何も疲れることはしていない」と思われるかもしれませんが、実際はそうではないということなのです。
脳疲労が深刻化すると、徐々に脳の働きは鈍っていきます。さらにひどくなると、感情のコントロールが難しくなったり、記憶力や集中力が著しく落ちたりと、日常生活にも支障をきたすリスクもあります。もはや仕事どころか、人生の満足度まで下げかねないのです。
新しい休み方「デジタルデトックス」の効果
■脳疲労を癒して本来のパフォーマンスを発揮する
では、この脳疲労をどうケアしていくべきなのか。私が理事を務める(一社)日本デジタルデトックス協会では、デジタルデトックスを脳疲労の蓄積を防ぐ「新しい休み方」として、次のように定義しています。
①一定期間、スマホやPCなどのデジタル機器と距離を置くことで、脳疲労など心身にかかるストレスを軽減し、現実世界でのコミュニケーションや自然との繫がりにフォーカスすること。
②デジタル機器利用時には、できるだけ心身への負荷がかからないような使い方をすること。
企業の講演に赴くと、「うちの会社ではDXを推進している。デジタルデトックスなんてできるわけがないじゃないか」といった趣旨のご意見をいただくことがあります。しかし、私はDXの時代にこそデジタルデトックス(DD)が必要だと信じています。
その理由はシンプルで、これまでに述べた通り、現代人の多くが脳疲労を抱えているためです。そして現代において脳疲労をもたらす主な要因は、スマホなどのデジタル機器です。
デジタル機器から断続的に新しい情報がランダムに届けられ、私たちは本能的に強く反応してしまうため、自分は休んでいるつもりだと思っても脳は慌ただしく情報処理をしている状態にあります。つまり、まったく休めていないのです。
<デジタルデトックスの効果>
- 気持ちがスッキリする
- 目の疲れが取れる
- 頭(脳)の疲れが取れる
- 睡眠の質が良くなる
- ストレスが減る
- 安心感が増す
- 想像力(創造力)が高まる
- ひらめきが良くなる
- 五感がさえる
- 幸せな気持ちになれる

組織でデジタル化を推し進めるのであれば、必然的にデジタルからくる疲れを継続的に取り除く必要があります。そうでなければ、そもそもDX施策が人にとって「サステナブル」でないものになってしまうでしょう。
■注目される「マイクロブレイク」とは
デジタルデトックス協会では1泊以上のデジタルデトックス・プログラムを提供していますが、必ずしも長期間やらないと意味がないわけではありません。むしろ、日々の生活のなかでこまめにデジタル休憩を取り入れることのほうが重要です。
マイクロブレイクとは、短時間の休憩を取り入れることで脳の疲労回復を促進する休息法です。仕事や学習の合間に数分間の休憩を挟むことで、脳の集中力を維持し、パフォーマンスを向上させることが分かっています。
マイクロブレイクは、特に長時間のデスクワークが続く現代の職場において非常に重要です。こまめに短い休憩を取ることによって、脳がリセットされ、次の作業に対する集中力が格段に高まります。
海外の調査結果をみると、職場での休憩時間中、ほとんどの方がSNSを見て過ごしているそうです。また私生活でも移動中、お手洗い、就寝前と、少しでもスキマ時間ができればスマホを取り出す方が多いのではないでしょうか。この時間を「スマホのお休み」とするだけでも、脳は一時の休息をとることができます。脳に余白が生まれることで、新たなひらめきも生まれるかもしれませんね。
■情報休暇の重要性
海外では、「スクリーン無呼吸」という言葉があります。メールチェック中の呼吸と心拍数を計測した調査では、被験者の8割の呼吸が同様に浅くなったり、一時的に止まっていたりしたのです。
メールチェックという日常的な行為でも、いかに私たちの心身は「緊張モード」に陥っているかがわかります。
カリフォルニア大学アーバイン校の研究によれば、仕事のメールを定期的にチェックする人は、メールを遮断して働く人よりもストレス度が高く、集中力が低い傾向にあるとわかっています。
メールチェック中の被験者は心拍数が高く、警戒状態に留まっていた一方で、5日間メールでのやり取りを休止する「メール休暇」を取った人たちの心拍数は比較的平常で、自然な変化が見られたそうです。
メールを頻繁に確認しない人はマルチタスクに陥ることなく、比較的作業に集中できていたことがわかります。5日間のメール休暇を終えて仕事に戻ってきた参加者たちの多くは、「ほとんどのメールは重要ではないと気づいた」と感想を語ったそうです。
いまこそ組織で「新しい休み方」を実装しよう
今後、組織に求められるのは脳疲労やそこから生じる燃え尽き(バーンアウト)を防ぐために必要な戦略的な休養です。次世代のビジネスパーソンにとっても、新たな必須スキルになると私は考えています。
企業が新時代の休息について励行し、社員が自らのメンタルヘルスを守るための知識を提供することで、長期的にはプレゼンティーズムや休職のリスクを減らし、職場の生産性や創造性をもたらすはずです。
AIをはじめ、デジタル化がどれだけ推進されても、ビジネスの中心には「人」が在るべきです。その「人」が疲弊して燃え尽きてしまわぬよう、今日からできる休息の方法を考え、組織内で実践してみてはいかがでしょうか?
エンゲージメントの向上も期待される
デジタルから離れ、休息する時間を設けることで、脳疲労を軽減し、心身へのストレスを緩和できます。結果的に、集中力が高まり、業務効率も向上します。オフラインの時間を組織で取り入れることで、組織内のコミュニケーションが活性化し、信頼関係の構築にもつながります。
デジタルデトックスのような「良質な暇(休息)」を取り入れることは、個々の健康を守るためだけではなく、組織全体の活力を高めます。戦略的な休養を通じて、より良い職場環境と高いエンゲージメントを築いていきましょう。
【執筆者プロフィール】
森下 彰大(もりした しょうだい)氏
一般社団法人日本デジタルデトックス協会理事 / 編集者 / 『戦略的暇』著者 / Voicyパーソナリティ
1992年、岐阜県養老町生まれ。中京大学国際英語学科を卒業。在学中にアメリカの大学に1年間留学し、マーケティングと心理学を専攻。
現在は「クーリエ・ジャポン」の編集者として、ウェルビーイングや企業文化の醸成を中心にリサーチ・取材・執筆活動を行う。
(一社)日本デジタルデトックス協会では企業・教育機関向けの講義やデジタルデトックス(DD)体験イベントを提供する。
米留学中にDDが今後の「新しい休み方」になると直感し、実践と研究を開始する。しかし社会人になり自身がデジタル疲れに悩まされるように。体調の悪化から危機感を持ち、会社員生活を続けながら小規模なDDイベントを始める。その過程で、「今の私たちに足りていないのは、余白(一時休止)ではないか」と考えるようになり、戦略的に余白―暇を作り出すための方法を模索。多忙な現代社会の中で人生を変えるための「戦略的“暇”」を提唱している。
2020年より日本初となるDDを専門的に学び実践する「デジタルデトックス・アドバイザー®︎養成講座」を開講。のべ100名以上の修了生を輩出している(2025年時点)。

関連商品
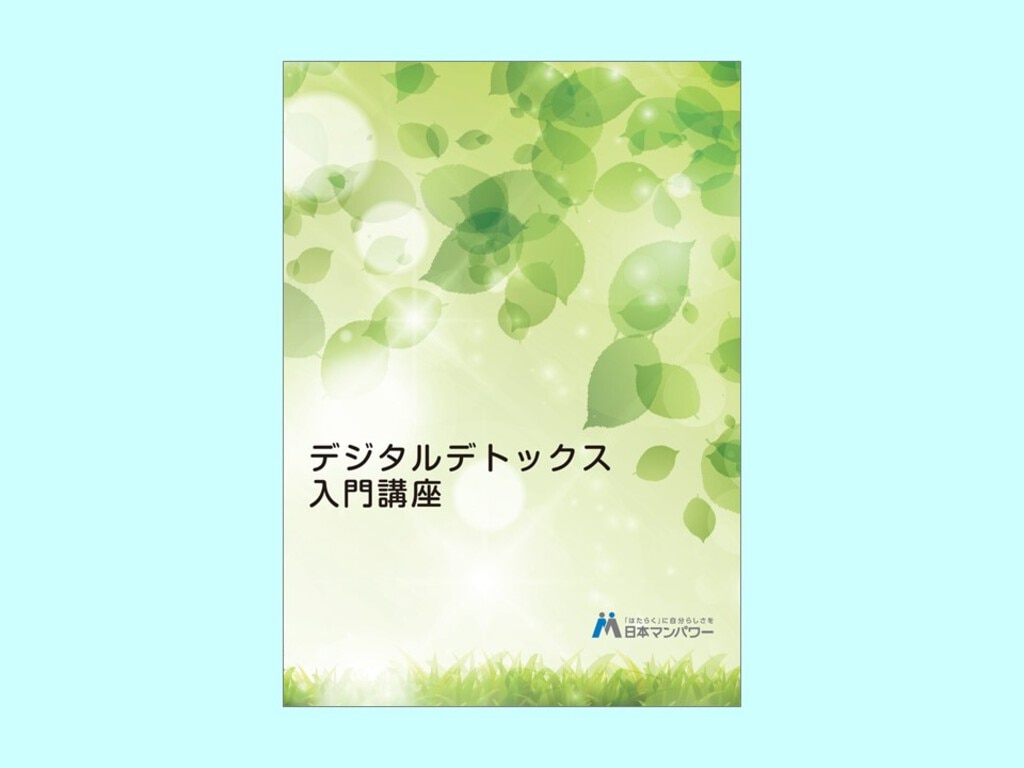
『デジタルデトックス入門講座』
「デジタルデトックス」とは、デジタル機器を完全に手放すことではなく、必要なときに効率的に活用し、一時的にデジタル機器と距離を置いてストレスや脳疲労を軽減しようという取り組みです。
デジタルデバイスとの上手な付き合い方を学び、ストレスを低減させます。また、デジタルデトックスの理解、実践を通じてウェルビーイングな状態を実現します。
● 受講期間 2ヵ月 ● 法人受講料 12,100円
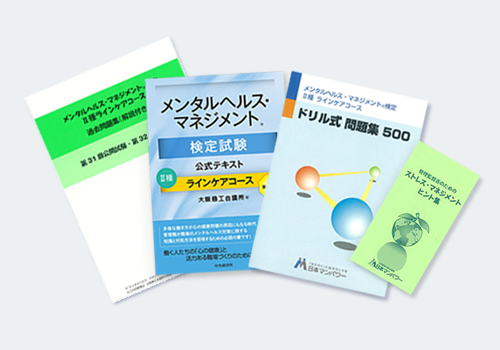
メンタルヘルス・マネジメント(R)検定II種ラインケアコース
職場における「心の健康管理」への関心が高まっており、企業の人事・労務管理におけるメンタルヘルス対策の推進が重要な課題となっています。本講座では、大阪商工会議所主催の検定試験合格を目標とし、職場のメンタルヘルスに関する基礎知識や、ストレスチェックの実施方法、部下に対する具体的なケアの手法などを学びます。
● 受講期間 2ヵ月 ● 法人受講料 12,650円
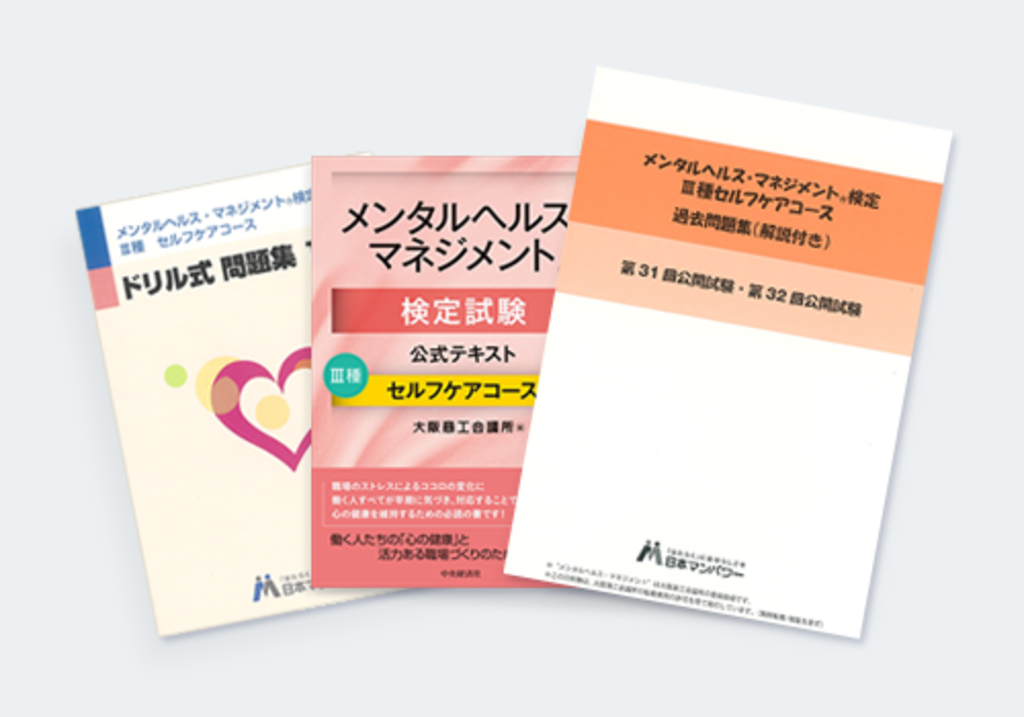
メンタルヘルス・マネジメント(R)検定III種セルフケアコース
職場における「心の健康管理」への関心が高まっています。本講座では、自らのストレス状況を把握することにより、不調に早期に気づき、自らケアを行い、必要であれば助けを求めることができるよう正しい知識と具体的な方法を学びます。
● 受講期間 2ヵ月 ● 法人受講料 12,100円
組織と個人の成長を
私たち日本マンパワーがご支援いたします
下記のページよりご確認ください
お役立ち資料はこちらから
当社が開催するイベント情報をお届けします
© Nippon Manpower Co., Ltd. All rights reserved.

